


会社口座残高2千円



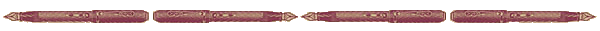 |
|
「ojisan。会社は大丈夫?」 新しい事務所を借りた私の所に、Aさんが顔を出した。 「最近、仕事なくてねぇ。」 「お金、残ってる?。」 「そこに、会社の預金通帳が入っているよ。」 Aさんは、引出しから会社の預金通帳を取り出した。 「ojisan。残高知ってるの?」 「・・・」 「2千円しか残ってないよ。」 PenPointという新しいOSは、私に幸運をもたらしてくれるはずであった。すべてがうまく行きそうに見えていた。OSを開発した米国GO社の日本支社も出来た。ソフト開発用キットの用意 も終わった。日本語のマニュアル作成も一段落して、販売が始まろうとしていた。新OSのためのソフト開発講習会も既に始めていた。関連商品の日本語化も終わっていた。職をなくしてうろうろしていた私を救ってくれたのは、今では一部上場企業にまで成長したS社であった。そこで、私は、この新しいOSを担当していた。 日本のパソコンメーカーは、ほとんどすべてがハードウェアの開発を進めていた。一部の商品は市場に出始めていた。手書き用のペンで、すべての制御をしようとするパソコンである。完全なオブジェクト指向、人間の感性に合った紙のようなインターフェイス、ネットワークによる同期を意識した設計。今から見ても、時代の最先端を行く技術が多い。 私は、そのOSを利用したパソコンが市場で反響を呼ぶと思い、会社を設立した(他にも事情があったのだが、またの機会にしよう)。日本の誰よりも先を歩いていると感じていた。ソフト開発も受託した。 最大手のN社が、ハードウェアの新製品を開発した。プレスリリース前であったが秘密厳守のもとに、新OSによる開発を進めていたソフト企業が呼ばれた。ハードウェアだけでは、商品は売れない。その上で動くソフトが必要である。ソフト開発企業の協力が欠かせない。N社は、超大企業であるが、小さなソフトハウスも大切にしていた。 新製品は、従来のパソコンからは想像できないくらいに小型軽量であった。モバイルという言葉が、ぽろりぽろりと使われるようにはなっていたが、まだまだ移動型パソコンとでも呼ぶ方が 理解されやすい時代であった。N社の既製品から見ても半分のサイズになっていた。その新製品は、モバイルパソコンの始まりとも言えるものであった。 新製品のプレスリリース直前になって、1つの知らせが届いた。米国GO社が買収されたという知らせだ。確かに、いくらシリコンバレーとはいえ、売上げゼロで、OS開発のために多くの 技術者を抱え続けるのは大変だったのだろう。買収したのは、AT&Tが出資するEO社。 まもなくEO社の代表が日本に乗り込んできて説明会を開いた。開発は継続すると宣言した。しかし、EO社は、競合する別系列の製品開発も進めていたので、関係各社には動揺が広がった。N社の新製品は、プレスリリースされることなく、お蔵入りになってしまった(1台くらい博物館に寄付して欲しい・・・日の目を見ずに忘れ去られるには惜しいマシーンだった)。 しかし、私達のソフト開発は続いていた。このOSにくっついて行こうと決めたわけだから、どこの企業が出資しようが所有しようが関係ない。私の新会社は、PenPointOSに関連するビジネスを目的として設立したのだ。技術者はアーティストでなければならないという信念のもとに、アートを意味するラテン語を会社名にした。「人生は短し、されど芸術は長し」というラテン語の「芸術」という言葉を使った。 また新しいニュースが届いた。EO社が、AT&T社に吸収されてしまった。そして、まもなく最後のニュースが、突然舞い込んだ。PenPointOSは開発中止というニュースである。 開発元の米国GO社は、解散。日本支社へは、社内の備品を売って、社員の最後の給与を支払うようにという知らせが届いた(そうだ)。机や椅子からネットワークまで、すべてが叩き売りであった。 (閑話休題)これが「たった一人のLAN」の始まりである。 こうして、私の目論見は外れた。開発途中のプロジェクトは、ストップした。製品が完成していないのだから、請求書を書くわけにもゆかない。入金予定がすべてなくなった。資本金も使い果たした。 Aさんが引出しから取り出した会社の預金通帳、口座残高は2千円であった。社員の給与や家賃どころか、電話代も支払えない。 そんな話しを、新製品の発表を中止した某N社の中央研究所で講演することになるとは、その時は思いもしなかった。明日から、どうやって生きて行こうかと考えるのが精一杯であった。そんな時に、ふらりと入って来た知り合いの営業マンによって救われたのだが、その話は、また書こう。 このお話しは、日本の全パソコンメーカーが関わり、そして消えて行ったOSの物語だから、もっと詳しい人達が数多く居る。順序が違う!という指摘があるかも知れない。私も書いていて自信がない(日記でチェックすれば確実なのにと思いつつ、面倒なのでやめた)。
|
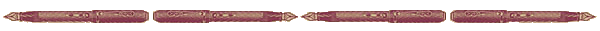 |


