


法界坊の鐘



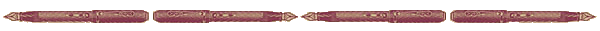 | |||
|
2000年の秋、新しく引っ越したアパートの近くで晩御飯を食べに出かけた。食堂のカウンターの隣りでは、一人の女性が焼酎をあけながら、旅の一座と回っている子供が今晩帰って来ると話しながら待っていた。子供がどうしても芝居がしたいと言うので、旅の一座に着いて行くことを許したらしい。まだ子供は小学生。旅の先々で学校に行っているそうだ。私が御飯を食べ終わっても、まだ子供は現れなかった。きっと、お母さんは朝までだって飲みながら待っているだろう。夜遅く、アパートに帰って来ると、日本髪に着物姿の艶やかなお姉さんと出会うこともある。そんな風景が、どこか似合う下町。その頃、近くの公園に芝居小屋が出来つつあった。 江戸より中仙道を下って第63宿目の宿場町が、鳥居本の宿である。かって、木曽路を旅した旅人達が、琵琶湖を望みながら磨針峠(すりはりとうげ)を越える。この峠を越えると、京の都までは平坦な道となる。峠を下ると、多賀大社の鳥居があった。ここが鳥居本の宿である。江戸時代には何軒もの旅籠が軒を連ねていたらしい。子供の頃には1軒くらい残っていた気もするが、今ではかっての旅籠が並んだ町の面影はない。 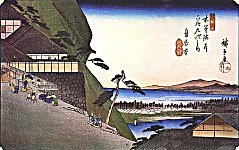 この宿場の入口に、上品寺(じょうぼんじ)という寺がある。今では、気をつけていないと、すぐに通り過ぎてしまうような目立たない寺である。 この寺の隣りで、私は生まれた。窓の外には、小さな釣鐘堂があり「法海坊の鐘」と呼ばれていた。小さい頃の遊び場だった。昔々、法海坊と呼ばれる偉~いお坊さんが建てたということ以外には、ほとんど何の知識も持っていなかった。国道8号線が新しく出来ることになり、私の家は立ち退くことになった。お寺の入口も、国道に削られて、ほとんど気付かれなくなった。 ところが、家を追い出されて浅草に引っ越してきた私は、突然、小さい頃の思い出に出くわすことになったのだ。墨田公園に建てられた芝居小屋には、中村座「隅田川続俤法界坊」(すみだがわ・にごちのおもかげ・ほうかいぼう)の幟が立っていた。 中村勘九郎が演じる法界坊は、釣鐘の建立を名目に集めた金で女道楽にふける破戒僧である。他人の恋路を邪魔して、切り殺されても、隅田川の渡し場で霊となって恋人達を悩ませるという物語だ。これは是非見に行きたいと思っていたが、残念ながらジャカルタに出かけてしまった。 この物語の史実は、もう少し美談である。法界坊の本当の名前は了海(法海坊)。上品寺の7代目の住職法海坊は、寺があまりにも荒れ果てていることを嘆き、江戸へ托鉢に出た。彼の法話に、吉原の花魁達が寄進をしてくれたので、鐘を造り、江戸から地車に乗せて引いて帰り、釣鐘堂を作ったと言われている。1769年のこと。 法界坊が吉原で有名だったことや、鐘のためにお金を集めたこと、彼が江戸で住んでいたのが「待乳山聖天(まつちやましょうてん)」だったことは、歌舞伎の物語と同じである。でも、立派な僧の物語では演目にならない。中村座の歌舞伎小屋は、まさに法界坊が住んでいた待乳山聖天の前に作られていた。 まさか、法界坊の鐘の下で生まれ育った自分が、そんな歌舞伎小屋がかかる法界坊の住んだ町に引っ越して来るとは思ってもみなかった。そんな縁があるのなら、私も法界坊と同じように、吉原で有名になりたいものである。
|
|||
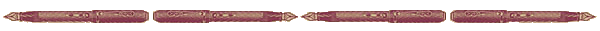 |


