


空母エンタプライズを通せ



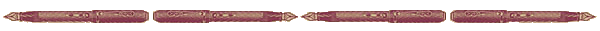 |
|
あれは、スラバヤの都市計画が終わった次の年だった。 電話がかかってきたのが、5月も終わりの頃だったと思う。Nさんから、突然、電話がはいった。来週、モンバサへ飛んで欲しいと言うぶっきりぼうな電話だ。よその会社の人間に、突然、来週アフリカまで飛べなどと命令口調で言われる筋合いはない。かりかり頭にきながらも、心の中では、アフリカへもう一度、行ってみたいという虫が頭を持ち上げ始めていた。 ガシャリと電話を切った後で、仕事の条件交渉を上司に頼んだ(小さい会社だったから、上司といっても社長だ。あんたが、ちょっと話しつけてよ、というわけだ)。もっとも、決してNさんは悪い人ではない。いつも、そんな調子なのだ。何も話さずに、自分で決めて、まわりを巻き込む性格なのだから、まあ、仕方がない。大急ぎで、日本での仕事を調整して、1週間後、私はケニアに向かっていた(しょせん暇人だったのだ)。今度の仕事は、橋を作る仕事だという。 ナイロビは、最高に気持ちの良い町だ。夜は、暖炉に火をくべる。朝になると、春先のような、爽やかな空気が流れる。セータを着込んで、外を動き回っているうちに、気温はぐんぐん上昇して行く。いつのまにかシャツ1枚になっている。1年の気候の変化が、1日サイクルにでもなった感じがする。 この町は、高地に位置しているので、高いビルに登ると、サバンナの大草原が広がっているのが見える。しかも、雲が眼下を流れていくのだ。よく仕事をさぼって、高いビルの上で、コーヒーを飲みながら、草原を見渡していた。町の治安は、とても悪かった。ウガンダからの難民があふれていた。町を歩けば、囲まれる。どこかへ逃れようとしても、店の中だろうが平気で入ってきて囲まれたままだ。まわりは、見て見ぬふり。脱出するのは、それなりに、一苦労ではある。後で聞いたら、大半の仲間が、金を巻き上げられていた。幸い、私は、いつも脱出に成功した。夜、車で外出する時も、エンストさせたら危険だよと言われた(ところが、借りた車は、実によくエンストした)。 仕事の目的地はモンバサ。ケニアの海岸の港町である。沖合いに、アラビアのダウ船が見えたりして異国情緒あふれる町だ。しかし、ここは暑い。 モンバサの町は、島になっている。西側の大陸とをつなぐ橋は出来ている。島から北へ向かう橋も、少し前に、日本の援助でできていた。ここには、浮橋がかかっていたのだが、今では使われなくなった浮橋が残っていた。さて、われわれの仕事は、この島から南へ橋をかける仕事であった。当時、ここはフェリーの渡し場になっていた。 地図で、モンバサを見てもらうと良い。モンバサを南へ下るとタンザニアに達する。つまり、ここに橋ができると、アフリカの東海岸にそって、道路が完成する。しかし、当時、タンザニアとの国境は閉鎖されていたから、実際には、フェリーに乗る人達は、近郊の通勤者である。 皆、よく歩く。信じられないくらいに歩く。ここでも交通調査をやったが、草原をつっきって、人が歩いているのを良くみかけた。私達にはわからないが、草原の中に、道の目印でもあるのだろうかと思うくらいに、ぞろぞろと同じ道筋を歩いている。ところが、どちらを見ても、町は見えない。地平線のかなたから、反対側の地平線のかなたまで、人が歩いている光景というのは、どこか変な感じがある。 仕事は、一見、単純そうに見えた。幅の狭い水路を横切って橋をかけて、渡し舟よりも便利にすればいいだけだ。 モンバサの海岸の砂は、本当に、真っ白である。きらきら輝いて、こんな白い砂があるのかと思うほどだ。最初、この海岸のホテルで、コーヒーを飲もうとした時に、テーブルに置いてある2つの壷を間違えたほどだ。片方は、砂糖のように真っ白、もう一方は、砂色。実は、茶色みを少し帯びた砂色の方が砂糖壷で、砂糖のように真っ白なのは、砂を入れた灰皿なのだ。初めての人は、皆、間違えるんですよと、知人は笑っていた。 ここは海の幸も美味しい。カニと一緒に、こん棒が出てきた時は、驚いたが、これでカニを叩き割るのだそうだ。皇太子(今の天皇)も泊まったことがあると聞いたが、こん棒でカニを叩き割ったのは、お付きの人だったのだろう。もっとも、私達は、そんな高級ホテルには泊まれない。町中の安ホテルである。まわりの治安が悪いので、運転手も、あまり遅い時間になると帰りたがらないような場所であった。 さて、問題は、どこにあったか。実は、まだ冷戦時代であった。アフリアの東側にあって、西側陣営の国は、ケニアしかなかった。インド洋に展開する米国の第六艦隊の母港が、実はモンバサだったのだ。それも、モンバサの南側にある水路を通って奥へ入ると、そこは湾になっていて、船を修理するには最適の場所であった。 まず、言われたのは「空母エンタープライズが通れるようにしろ」である。空母というのは、誰もが知っているように、非常に背が高い船である。これを通すには、橋桁を十分に高くしなければならない。 しかし、私達は日本の調査団である。日本は、戦時目的の援助を認めていない。つまり、設計の要件として、軍事的な理由は存在してはならないのだ。ケニア政府の要求は理解できる。しかし、そんな理由が、まったくないものとして、要求を実現する方法を模索しなければならない。とてつもなくボケた話しだ。第六艦隊によって平和が守られ、日本も、その恩恵を受けているはずなのに、そんなものが存在しないとして計画するなんてことの方が本当は変だ。 そこで、エンタプライズの代わりに、クイーンエリザベス号が停泊することに仮定した。実際には、どっちの船も沖止めだそうだ。客船の方は、たまに入港することもあるらしいが、空母の方は、軍事的に考えても、狭い水路の奥で停泊させるなんて真似は、絶対にしないだろう。だって、水路の途中で、艦船が爆破されて沈没したら、湾がふさがれてしまう。 いずれにしても、これらの船が、橋の下を通過できるようにするには、相当に高い橋を作らなければならない。ところが、水路の幅は狭いし、島も小さい。通常の傾斜で、橋へのアクセスを作ると、島の反対側か、それ以上先に、橋への上り口を作らなければならない。つまり、モンバサへの橋をわたると、モンバサの町を通りこしてしまっているというわけだ。 それなら、橋へのアクセスを、螺旋形にして、そこを車で登らせるという案が出てきた。まあ、車は勝手に登ってくれるから、なんとかなるかも知れない。しかし、歩行者は、どうすればいいのか。エレベータでもつけるしかない。しかし、朝の通勤ラッシュの時に、高さ100m以上のエレベータをフル稼動させて、人を運ぶなんて、あまりにも現実離れしている。 「空母を通れるようにしろ」という要求が出た段階で、困ったことになったのはわかっていた。橋そのものが、軍事的に考えれば不適当だったからだ。湾をふさぐにはもってこいの構造物である。空爆しようが、ゲリラが爆破しようが、簡単に軍港の機能を麻痺させることができる。 要するに、暗にトンネルが求められていたのだ。しかし、この水路は狭いとはいっても、大型艦船が通過できるだけの水深がある。トンネルにしたところで、相当に深いトンネルを用意しなければならない。トンネルを掘るか、トンネルを作って沈めるか、非常に大規模な工事になる。 だんだんわかってきたことがある。日本は、アフリカの東側に位置している唯一の西側陣営を援助するために、何かのプロジェクトを進めたい。しかし、その予算には限界がある(トンネル建設できるほどはない)。そこで、橋の案が浮上したが、ケニア側の軍関係者は、軍事的に橋の建設に反対している。と言うことは、我々の立場は、何なんだ~。
|
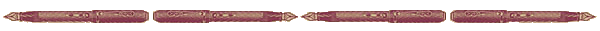 |


