


辞書をかついで・・・



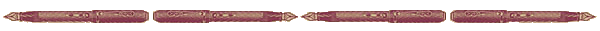 |
|
今回は、どうやってインドネシア語を覚えたかのお話しをしよう。まあ、多くの人達が、同じようにしているから(少なくとも当時の若者達は・・・と訂正)、特に目新しい話しではないが、あんまり誰も話さないお話しだ。 外国へ出かけると、街の人達とおしゃべりがしたくなる。おしゃべりがしたいから、なんとか地元の言葉を覚えようとする。ちょっとした会話ができるようになるだけで、とても楽しい。日本の英語教育の欠陥は、言葉を覚える楽しさを教えてくれなかったことにある。知らない人と、話しができる楽しさを教えてくれていたら、もっと英語を勉強していただろうと思う。 しかし、外国で、仕事をしながら、言葉を勉強するのは意外に大変なのだ。仕事の言葉が、その国の言葉なら、仕事の中で必死で覚えるだろう。しかし、たいていの国で、ビジネスは英語で進む(と言うか、英語圏以外には行ったことがないだけなのだが)。仕事で積極的に使うことがないと、言葉なんて覚えない。英語ですら、まともに話せないのだから。 ジャカルタに着いて、最初に学習書と辞書を買ってきた。今は、日本語とインドネシア語の辞書も、比較的簡単に手に入るようになったし、日本語で書かれた学習書も出ている。しかし、当時は、今にもバラバラに分解しそうな綴じ方の、英語・インドネシア語、インドネシア語・英語の辞書しか手に入らなかった。紙も悪いから、2冊積み上げると、相当な厚さだ。しかも、英語の説明がすらすら読めるわけがないから、英語と日本語の辞書も一緒に使うしかない。 幸いインドネシア語は、アルファベットを使うので(歴史的にはアルファベットを採用したのでと言うのが正確だが)、単語の並び方はわかる(タイ語だと、文字も読めないから大変だ)。しかし、単語が変化すると、もう辞書がひけなくなる。特に、会話形と辞書形とが違っているので大変であった。 同じ頃に、同世代の仲間が居たので(前にも書いたが)、毎日、1つでも多くの単語を覚えたことを互いに自慢できた。街へ出て、ちょっと違った単語がヒアリングできたりすると、それだけで「勝った!」という感じで、言葉を覚えるのが競争になったのが、最も大きな励みではあった。 家庭教師も雇った。家庭教師というのも、話すのが楽しくなくちゃしょうがないので、男の私は、女性教師を頼んだ(しかし、今までの経験では、この魂胆は効果的ではない・・・教えるのがうまい人が本当は一番良い)。 でも、まあ、男達が考えることは、だいたい同じところに行き着く。可愛いお姉ちゃんと、お友達になりながら、会話を勉強しようというわけだ。だが、こういう国では、普通のお姉ちゃんとお友達になるのは、まず不可能(であった・・・最近は変わってきた)。回教国である。ベールを被ったお祈りが日常の国(大型コンピュータの横で、お祈りの時間にぶつかった時は、最初は違和感があった)。普通のお姉ちゃんが、外人の男とお友達になるなんて、もってのほかである。 そうなると、私たちの相手をしてくれるのは、玄人さんしか居ない。昔は(今は違うよ!)、ジャカルタで仕事をしている女性の半数以上が売春婦と言われていた。機会は、まわりにもいくらでもあった。一番低級なのは、ムシロで囲いがあるだけの店(さすがに近づけなかったが)。次は、コーヒーショップ(今は、違うから、間違えないように!)。コーヒーという看板の店へ入ると、内装は喫茶店である。しかし、すわったとたんに、コーヒーの注文より前に、女性達に囲まれる(恐いものがあった・・・コーヒーだけ飲みたいのだ)。ビリヤード屋のお姉ちゃんも似たようなもの(であった)。一般的なのは、金魚鉢。女性が、ガラスの向こうの雛壇にすわっていて、こちら側から男達が女の子を選ぶ店。もう少し高級になると、クラブ。これは銀座のクラブと同じ。お金をつぎ込んだからといって、誘いにのってくれるかどうかは分からない(費用対効果は、銀座よりも、場末の港町程度かな)。私が見たのは、そこまでだが、高級置き屋もあるそうだ。しかし、巷では、日本人は金持ちでも、発展途上国の金持ちは桁が違う。そんな人達の店へ行くと、惨めになるだけだと友人が話していた。 私達は(複数形を使って自己弁護をする)、金魚鉢のある、お風呂屋さんへよく通った。晩飯が終わると、分厚い辞書を何冊も担いで、黄色いマーカーペンを持って、お風呂屋さんへ向かう。個室に入れば、一定時間は、お話しができる(まあ、他にもすることはあるが)。辞書を並べて、言葉のお勉強である。楽しい時間を過ごそうと思えば、言葉を覚えるしかない。家庭教師を雇う値段よりも安かった。入場料なるしょば代を払い、あとの値段は、女の子と交渉だ。たまに、「明日も来なよ」と言って、入場料分まで返してくれる女の子も居たりした(こういうのって感激するんだよね・・・そして、通い続ける)。 こういう所で働いている女の子は、ほとんどのケースが、子供を抱えて離婚した女性である。田舎に残してきた子供の写真を見せながら、学校の成績が良くなった話しや、年老いた両親の話しなどをしていた。田舎では、もちろん、こんな仕事をしていることは誰にも知られていない。断食明けには、子供達へのお土産を一杯買って田舎へ帰る。ジャカルタへ出てくる日には、子供に引き止められないように、寝ている間に抜け出して来るのだそうだ。ここは、人生模様のすべてが凝縮されたような世界だから、とても簡単には書ききれない(小説が、いくつも書けそうな気になる)。 こういう店では、金魚鉢のこちら側の客が、女の子を自由に指名するように思われている。旅行者の場合は、そうかも知れない。しかし、長く居ると、そんな真似は出来ない。客の方が選ばれる。例え、最初は選んだつもりになったとしても、次回の選択肢はない。女の子同士で、客の取り合いをしないのが不文律になっているから、浮気はできない(?)。長期滞在で新たに赴任して来る人が居ると、皆が、最初が肝心なんだよとアドバイスするのだが、若い男達は、女の子がずらりと並んだ店の中で、聞く耳をなくしているのが普通だ。そして、見かけで選んで失敗する(なんで、こういう時には、皆、面食いなんだろう・・・まぁ、それしか基準がないから仕方ないか)。遊ぶ前に、置き屋の女将やオヤジと友達になって、紹介してもらうのが、結局は楽しい単身生活のコツなのだと知るには、時間がかかる。 やっぱり、本能の欲望に従って行動すると、言葉を覚えるのも実に早い(ような気がしただけかいなぁ?)。しかし、こうやって覚えるとと、最初は、下品な街言葉を覚えることになる。とても、仕事の場では使えない。お里が知れるというわけだ。もっとも、インドネシア語の場合は、男言葉と女言葉に、差が無い(若干はある)から、まだ助かる。タイで、これをやると、女言葉のなまりがしっかりと身について、直すのが大変になる(タイの女性語が得意な日本人男性は多い)。 たびたび、今は違うよ(!)という話しを書いたが、実は、もうだいぶ昔に、インドネシアでは、売春禁止となった。赤線の火が消える日は、当然、「最後だ~!」であった。女の子達は、明日からの生活を心配しながらも、客に連絡先を渡すことに余念がなかった。表向きは禁止されたとしても、裏の世界は生き残るというわけである。そして、次の日から、すべての店が閉まった。玄関に、暖簾が地面までかかった独特の店構え(昔の日本の商店が、夏の日差しを避けるために、暖簾を地面までたらしていたが、それと同じ)が、見られなくなった。 しかし、表からは消えても、お目こぼしのある地区も残っていた。表から見たのでは、明かりも消えた普通の家。暗い入り口を奥まで入って行くと(あるいは、暗い階段を登って行くと)、そこには金魚鉢の名残が残っていた。ガラスにカーテンをかけたり、目張りをしているが、ちゃんと、中が覗けるようになっていた。その後、例の病気がアジアでも心配されるようになり、どうなったかは知らない。そんな店は、皆、火が消えたようだという噂は聞いた。私も、長期滞在しなくなって久しい。もっとも、男達が、そんな遊びをしなくなったとは言わない。ちょっと、最近は違ってきた。でも、その話しは書かないことにしよう(裏切り者とは呼ばれたくない)。 そんなわけで、何とか言葉を覚えた。マーカーペンを引きまくった辞書は、もう分解しかかっている。他にも、ちゃんと、ノートに何冊も書き取りもしたんだよ。インドネシア語は、だいたい3ヶ月で、日常会話はできるようになる。言葉というのは不思議だなと思うのは、一定の速度で覚えて行くものではなさそうだ。ある単語数に達すると、突然、日常会話ができるようになる。またしばらくは、いくら単語を覚えても、進歩を感じられない。そして、ある日、突然、理解の範囲が広がる。なんか、突然にして開く壁が、いくつもあるかのようだ。しかし、もっぱら会話から言葉を覚えたので、文章が読めない。英語とは、まったく逆だ。文字が読めなくて話しがわかるというのは、文盲と呼ぶのではなかったか。よく友人達と、自分達は文盲だと話す。
|
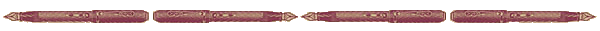 |


