


ドキュメンタリのお話し



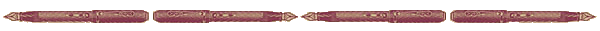 |
|
NHKのドキュメンタリーに出演したことがある。当時のNHKの番組では、7時のニュースが終わると、7時半からドミュメンタリーが放送されていた。ゴールデンタイムである。それに、脇役で出演したことがある。これは、とっとも古いお話し。六本木に居た頃に、NHKの人達が訪ねて来た話しを、前にちょっと書いたが、その続きだ。主役は、後に、サウジアラビアの国境を引きに出かけた男。 NHKのディレクターは、面白い話しはないかと探していた。大学闘争の時代が終わりつつあった。しかし、先輩のK氏は、まだこだわっていた。正義感の強いタイプだった。私などは、それなりに革命ごっこを楽しんだのだから、次の遊びを考えればいいさ程度の軽薄さだったが、彼は、自分の生き方を、理想の中に求めようとしていた。別に、学生運動の活動家だったわけではない。大学を否定する言葉を叫んだ者として、それを曲げることができなかったのだ。 国立T大学は、2年間の教養過程と、2年間の専門課程に分かれていて、キャンパスも変わる。私が大学に入学した時、彼は先輩であった。クラブでは、彼は人間、私は虫けらという体育会系の掟は変わらない。しかし、すぐに学年は追い越した。2年間の教養過程では、2回の留年と、2年の休学、それに降年といって2年生から1年生へ落第する制度があった。これを組み合わせると、休学届けを忘れたとしても、6年間過ごせることになる(と記憶している・・・もう、だいぶ不確かになっているが)。専門過程と合わせれば、社会に出るまで12年間の執行猶予期間が得られる。ところが、彼は、教養過程で、既に6年を過ごしていた。勉強家ではあった(?)。 残された方法は、退学願いを提出することだ。退学にしておけば、「深く反省して、もう一度、学校に戻りたい」と泣きを入れれば、入学試験を受けなくても再入学させてくれる(ことがある?)。それに、退学届けを出せば、国立T大学中退と、経歴書に書くことができる。これだけでも、就職には有利だ。ところが、退学願いを提出しておかないと、「除籍」という処分を受ける。これだと、「そんな人は、うちの大学に入学した記録はありません」と言われることになる。いくら、まがったことが嫌いとは言っても、たった1枚の書類を提出すれば済む話しなのだ。皆が、退学届けを出すように、何度も説得した。しかし、頑固者の彼は、それをしなかった。 彼の家は軍人一家である。お父さんはもちろんだが、曾祖父の名前は、明治の歴史に欠かせないほど有名な軍人である。そんな家に育ったT大生が、除籍処分を受ける。学生運動の挫折。その中で、蝶を追うことに賭けた彼の青春は、ドキュメンタリーに、ぴったりの題材だった。NHKのディレクターやカメラマンが、話しにやってきた。私は、脇役でも、顎足付きの旅が出来れば、それで楽しいと思っていた。 ストーリー展開は決まった。大学闘争、そこでの挫折。自然の中で蝶を追う若者。正義を貫く生き方に対して、大学から除籍処分が宣告される。時代背景を考えても、視聴率の稼げる話しだ。自然の中で、花や蝶とたわむれる若者達、官僚機構的な大学との対比。悪くはない。ところで、その自然を、どこで撮影するかという話しになった。 カメラマンは、新婚旅行で出かけたことのある網走の原生花園へ、もう一度、行ってみたいと言う。汽車なら、青函連絡船を乗り継いでの長旅だ。飛行機は、高くて、なかなか乗れない(時代であった)。これを取材名目で、出張しようというわけだ。私達は、反対した。原生花園へは、以前にも行ったことがあり、もう一度、行きたい場所ではある。しかし、そこでは蝶は採れない。蝶の生態を知っている人、昆虫について知ってる人が、TVを見ていたら、あまりにも無理のある背景だとすぐにわかってしまう。しかし、結局は、カメラマンの意見に押し切られた。 原生花園の近くに宿をとった。しかし、オホーツクの海は、どんより曇っている。カメラマンのイメージの中では、光りあふれる青空のもとで、原生花園のお花畑の中を、蝶を採集する網をもった若者2人が、かけまわらなければならない。 網走の町は、厚く雲に覆われていた。何もすることはない。ディレクターとカメラマン、それに、K氏と私、丁度4人居る。毎日、毎日、朝から夜中まで、麻雀を続けながら晴れるのを待っていた。麻雀に疲れてくると、網走の町まで、お茶を飲みに出かける。 今の、網走の町ではない。ずっと、ずっと昔の話しだから許して欲しい。網走の町中を、あちこち歩いたが、みつかったのは、国道沿いにある、いかにも小さなコーヒー&スナックの店。カウンターがあって、その向こうにマスターのオバサンが居る(表現が変かな)。「コーヒーありますか」と聞く。オバサンは「コーヒーはないんだよ」と答える。「でも、紅茶なら出来るけど・・・」と言うオバサンに従って、紅茶を注文した。 オバサンは、お湯をたっぷり沸かすと、紅茶カップを4つ用意した。そこに、熱いお湯をそそぐ。その時、おばさんが取り出したのは、最後の1個になってしまったLIPTONのティーバックであった。「まさか、ティーバックが1つということはないよな」「どこかにしまってあるか、買いに行くんじゃないかな」、我々は、ボソボソ話していた。しかし、オバサンは、お湯が注がれた4つのカップに、次々に、そのたった1個のティーバックを、ポチャン、ポチャンとつけはじめた。少し、お湯に色がついたかなと思うと、次のカップ、そして、次のカップ。1個のティバックで、見事に、4杯の紅茶カップの中身を、紅茶色にさせたのだ。請求された金額は、しっかり4杯分の紅茶の値段であった。 1週間、網走で麻雀を続けていたが、取材旅行のタイムリミットになりつつあった。明日は、何が何でも撮影して、東京へ帰ろうと、ディレクターが宣言した翌朝、空は、くっりと晴れ上がった。青空が広がり、太陽の光があふれている。K氏と私は、蝶を採集する網をふりながら、砂地の土地を何度も走った。珍しい蝶は、こんな所には居ない。実際に採集したくなるような蝶は居ないのだ。でも、画面で見ると、楽しそうに蝶を追う若者2人に見えた。 NHKドキュメンタリー「蝶と青春」の物語。 それなりの評判ではあった。これを見た人の感想が、何かの本にも書かれている。番組の内容は、正確である。テーマは、如何にもシリアスだ。しかし、K氏は、そんなシリアスなタイプではない。彼は、あちこちの国で仕事をしながら、ほとんどの国に出かけたことを自慢している(先日会ったら、ブータンの話しをしていた)。今でも、蝶の切手だけは、世界中で集めまくっているらしい。
|
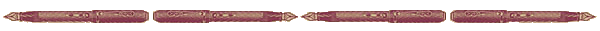 |


