


ぎふちょう



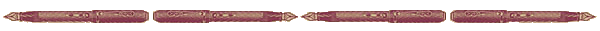 |
|
春になると「ぎふちょう」という美しい蝶が飛び始める。かっては、あちこちで見られた蝶だ。しかし、今では、この蝶をみつけるのは奇跡に近い。 私は、「ぎふちょう」と呼ばれる蝶に出会って、蝶の世界にのめり込んで行った。高校時代のことだ。雑木林の斜面の日だまりに、「ぎふちょう」が乱舞していた(乱舞なんて言葉を使うのは蝶屋だけかも知れない。要するにたくさん飛んでいたということだ)。網を持って追いかける。長く伸びた棒の先にある網の位置が、自分の手と同じようにな距離感で認識できるようになると、蝶をつかまえることができる。もしかすると、剣道の間合いも同じような感じかも知れない(というのは勝手な想像だ)。 芽吹いたばかりの緑の中を飛ぶ、黄色いはねの「ぎふちょう」は、春の女神とも呼ばれる。日本には、「ぎふちょう」と「ひめぎふちょう」と呼ばれる似た種類の蝶がいる。「ぎふちょう」は中部から関西、「ひめぎふちょう」は中部から北に生息する(正確な分布は忘れたので、間違ったらごめんなさい)。 蝶は、その種類ごとに、幼虫時代に食べる植物が違っている。この蝶は「かんあおい」という植物を食べて成長する。「かんあおい」は、雑木林と田畑が接するあたりに自生していた。葵の葉をつやのある色にしたような感じで背丈の低い草である(いいかげんな表現だなぁ)。 蝶は、一匹二匹とは数えない。一頭二頭と数える。高校一年生の頃、「ぎふちょう」を採集にでかければ、何頭でも採れた。網に入れた蝶のうち、標本として美しいものだけをつかまえて、三角紙と呼ばれるパラフィン紙に包む。 つかまえた蝶は、展翅という方法で標本にする。両方の翅(はね)をひろげて、パラフィン紙で位置を台に固定しておく。奇麗な標本にするには、触角の位置も整える。つかまえてから、なるべく早く展翅をしないと、翅をうまく動かせなくなる。その場合は、三角紙につつんだまま、湿気にあてるようにしたり、蝶の身体にお湯を注射したりする。しかし、そんなことになる前に、自然のままで標本にするのが良い。 高校3年生頃になると、都会の近くで、「ぎふちょう」をみかけることは少なくなった。でも、山間では、まだまだ多く見かけた。大学時代になると、「ぎふちょう」の採集地は限られるようになってきた。大学を卒業する頃になると、奇麗な標本を作りたければ、卵から育てるしか方法がなくなりつつあった。卵から幼虫にし、蛹になるまで、「かんあおい」と呼ばれる食草(ショクソウと読む)と共に、育てるわけだ。食草は、別の植物では代用できないから、「ぎふちょう」を育てる時期になると、冷蔵庫には「かんあおい」が大量に詰め込まれることになる。 蝶の減少は乱獲が原因だと批判されたりもした。しかし、私は、そうは思わない。問題は、食草の方なのだ。食草を根こそぎ取られたら、蝶は生きて行けない。蝶屋と呼ばれる蝶採集が好きな人間達なら、蝶の生態を知っている。だから、絶対に食草を荒らしたりはしない。「ぎふちょう」が生育している土地の「かんあおい」を取ってしまったら、もう終わりなのだ。蝶は、食草を求めて移動できないし、「かんあおい」だって自然の中で1mも領域を広げるには100年の歳月が必要とも言われる。 「ぎふちょう」は、郊外の開発が進むにつれて、次第に消えて行った。今では、町の天然記念物に指定されていたりするが、絶滅に近い状態とも言える。最近は、「ぎふちょう」を育てて自然に戻そうという試みも行われているが、この蝶が育つ環境が失われつつある状況には変わりがない。 大切にしていた私の標本箱は、自分で管理しきれなくなったので、大学で教えている友人に寄付した。彼の家には、昆虫標本のための部屋が作ってある。彼が、大学で教えているのは、まったく違う分野だ。自分の病院を建てた医者の友人は、蝶のために1フロアを余分に作ったと言っていた。奥さんからは猛反発を受けたらしい。 時々、網を買ってきて、もう一度、蝶を採りに出かけてみたいなと思うことがある。昆虫店などの前を通ると、ちょっと足が止まる。インドネシアへ出かけ始めの頃は、網を持って行った時もあった。しかし、山を走り回るような体力は、もうない。そのうち、カメラでもかついで出かけてみようかとは思う。「ぎふちょう」の飛ぶ姿を、もう一度見てみたい。
(ぎふちょう) 
|
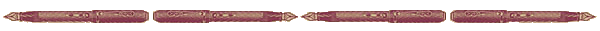 |


