


調査回収率は・・・



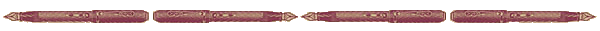 |
|
ジャカルタは、昔はバタビアと呼ばれていた。東インド会社の拠点である。だから、東西交易の品々が数多く残っている。有田や伊万里も、日本ではお目にかかれないようなものが、ここの博物館にはある。以前は、スラバヤ通りという名の泥棒横丁で、本物に出くわすこともあった。でも、今は、観光客相手の模造品である(模造品も好きだ)。東インド会社のロゴ「VOC」が入った陶器やレンゲを買ってきて、ラーメンを食べるのに使っている。 道路は、細い道が多かった。おばさん達が道端で話し込み、子供が駆け回る。物売りがけだるい声をあげながら通り過ぎる。子供の物売りが、箱から出した数本の煙草をバラ売りしに来る。屋台のおじさんが、日陰でぼんやりと客を待っている。荷車を引いた水牛が通り過ぎる。街の乱雑さの中で、自分が、ふと子供に戻ったような感じがする。小さい頃に見た風景が、そこにある。 そんな路地を歩いていると、今にもそこの角から、鼻水をたらしたいじめっ子が、棒でも持って飛び出してきそうに思えてしまう。 もう、今のジャカルタでは、そんな風景が見られることはない。高層ビルと行き交う車だけだ。町の骨組みになる幹線道路が整備されると、細い道を通る車は少なくなる。通り過ぎる旅行者は、表通りの町並みを眺めるだけで、裏通りの生活を思い描くことはない。最も良い時代にジャカルタを歩き回った気がする。 街の中心部には、ソ連の援助で作られた巨大なクローバ型の立体交差から、道が東西に伸びていた。交差点は、ほとんどがロータリー形式になっていた。そのロータリーには、力強い巨大なモニュメントが建っている(こういうモニュメントは、独立時のような国造りに燃えている時に生まれる)。ソ連の次に入ってきた専門家集団はドイツ人達だった。日本人は、ドイツ人技術者達の次に登場したわけだ。 ジャカルタの道路計画を推進してきたドイツの技術者と話した。「もう、戻って来ないんですか」と私。「私達の仕事は、だいたい終わった。今度は、日本人が仕事をする番だよ」と彼。それから、約10年たった時、同じことを話している自分に気づいた。「もう、戻って来ないんですか」と、そのインドネシア人が聞いた。「もう日本人が仕事をする時代は終わったんだよ。これからは、あなた達が自分の国を作っていく番だよ」。 交通量調査といっても、車はほとんど走っていなかった。町の幹線でも、1時間に数台だった。しかし、経済成長を見ると、30万台~50万台の交通量になるのは、ほんの10年先だったのだ。 両側に大きな木が立並んで、道に日陰を落とす。幹には、夜でも目立つようにと白線が塗ってある。緑あふれる町並みだった。しかし、数台の車が通る時代から、何万台もの車が通る時代に向けて、その緑の多くをなくすしかなかった。道路建設に携わった年配の技術者が、建設後に、一人でこつこつと木を植えて歩いていた。「せめてもの罪滅ぼしですよ」と笑いながら(ず~っと後の話し)。 まず、ジャカルタの、あらゆる道で交通量調査を行った。人を集めるのも大変だ。役所の前には、仕事を求める失業者がごろごろしていたが、それなりに信頼できる調査員が必要であった。しかし、ここの大学生はエリートである。そんな手を汚す作業はしたくない。でも、小学校の先生や勤め人が集まった。交通量をカウントするだけの調査だったが、様々な問題があることがわかった。調査員が座る日陰が無い場所はどうするか。暑い中で、24時間調査である。夜中は、真っ暗闇。懐中電灯だけではなくて、アセチレンランプも必要だ。調査員の交通手段がない!、食事は?、水の配達は?。調査員が回教徒で、お祈りの時間が必要と言われたら?。 なんとか、交通量調査は終わった。次は、車の経路を調べなければならない。葉書によるアンケート票を配ることにした。まず、郵便料金を受取人払にしないと、誰も出してくれない。それを準備し、回収率も低めに想定し、いわゆる統計調査の方法に従って、有為水準の結果が得られるサンプル数を想定した。今日は、どこからどこへ行きますかという質問を書いた葉書を印刷する。何千枚もの葉書を地点別に分けて、番号をハンコでペタペタ打つ。そして、いよいよ調査開始である。 調査員が、ジャカルタのあちこちに配備された。葉書の配布枚数も、何台に1枚という形で設定してある。もし、不足することがあれば、届けなければならない。ジャカルタ中を走りまわった。時々、調査員全員が逃げてしまっている場所もある(でも、どうせ報告は、もっともらしい数字付きでまわってくるのだ)。調査のための地図を眺め、町を走り回っていると、そのうち町の道路に詳しくなる。 調査票の配布は終えた。回収されるのを待った。待った。待った。そして、戻って来た葉書は、3通であった。最初から、やり直しだ~!。 (*)こういうドタバタの中で、実務のノウハウはたまって行くものなんだろう。今では、機材準備から始まって、調査方法、調査員の集め方、チェック方法、等などのマニュアルが、何冊も整備できている。それぞれのマニュアルに書かれている細かな支持や注意は、失敗の中から得られたものが多い。
  
|
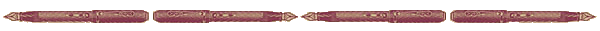 |


