


私の幽霊に会った人達



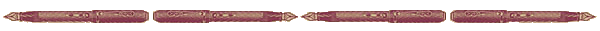 |
|
その頃の私は、金融関係のソフト会社の社長だった。バブルの、まっ盛りの頃である。絶頂期には、自分でも信じられないくらいの収入があった。今の3倍はあっただろう。それがなくなって、収入が、毎年ガンガン減って行くというのは、非常にきついものだ。だって、税金は前年分がかかってくるからね。もっとも、そんな収入は、すべて、「オジサ~ン」と呼んでくれた女の子達の、洋服、ハンドバック、アクセサリー、豪華な食事代に消えて行った。当時、1日に使ったお金の方が、今の月収より多かったことがあるのを思い出すと、馬鹿をやったもんだという気にもなるが、いい勉強だったのかも知れない。2度と、大きな会社の経営者なんかやりたくない。 収入もあったが、ストレスも強烈だった。毎日、鏡を見るのが恐かった。どんどん老け込んでいく自分と対面するからだ。給料に差をつけるとか、人員整理だとか、朝礼とか、すべて大嫌いだ。しかも、辞表を出す先もないのだ。住んでいる集合住宅で殺人事件がおこり、(当時は結婚していた)奥さんの精神状態もおかしくなった。大変な時期だった。毎晩、3時、4時に帰って風呂に入る。まあ、今でも時間帯は同じだが、精神状態が違う。そんな生活が続いていた。 風呂に入っていると、人の話し声が聞こえる。こんな夜中でも、騒いでいる部屋があるんだと思っていた。集合住宅の風呂場だ。しかも静かな夜中。他の部屋の声が響いたとしても不思議ではない。そんなことが時々あった。しかし、ある日、車を運転している最中に、同じ声が聞こえた瞬間に、これはヤバイ!とわかった。これは、幻聴だ。存在しない声が聞こえるのだ。でも、誰にも心配をかけないように黙っていた。会議中に幻聴が始まったりすると、ひたすら沈黙している以外になかった。 そして倒れた。倒れた記憶はない。救急車で運ばれている最中に気づいたのだ。風呂場で、悲鳴をあげて倒れたらしい。もっとも、救急隊に運ばれようとしている時に、私は、無意識で煙草の箱をつかんでいたらしい。倒れても、煙草だけは手放さなかったのだから、そう簡単に禁煙はできないだろう。それから、何度か意識不明になって、救急車で運ばれることがあり、ついに入院させられてしまった。原因は、はっきりしないままだが、ストレスがなくなったら、そんなこともなくなったのだから、精神的なものだったのだろう。 そんなある日、某大手物流会社の(その後社長になった)人が訪ねて来た。「先日、お茶の水駅で会った時に、顔色悪かったね。でも、話している最中に、ふっと消えてしまったんだけど、どこへ行ったの?」と聞かれた。私は、お茶の水駅には、最近近づいたことがないことを説明した。彼とは、10年以上前からの親しい付き合いだから、顔を間違えるようなことはない。「世の中には、同じ顔をした人が何人かは居るとか言われているじゃないですか」と話した。でも、彼が話し掛けた私(?)は、ちゃんと、私がするような応対をしていたというのだ。「話しも辻褄があっていたのに」と不思議そうな顔をして、私をみつめていた。 そこまでは、私も笑っていた。しかし、彼の次の一言で、笑いが止まった。「そう言えば、違っていたかも知れない。彼は、眼鏡の色が茶色だったよ。その眼鏡は、グレーだから、やっぱり人違いだったんだ」。実は、その前日、私は眼鏡を替えていた。それまで、茶色のレンズだった眼鏡を、グレーに作り替えていたのだ。あまりのことに、言葉を失っていた。 しばらくして、高校時代の親友から電話があった。私が別れの挨拶をしに来た夢を見た、何もなければ良いがと思って電話してみたというのだ。10数年間、年賀状のやり取りしかなかった友達だ。 やっぱり、意識不明で救急車で運ばれた時には、自分の幽霊が居たのかも知れない。だから、その時には、挨拶に行くかも知れないから冷たくしないで欲しい。 幻聴の言葉が、いつも同じ内容であるように感じているのだが、それが終わると、まったく覚えていない。だから、メモ用紙だのテープだのを持って、幻聴が起きた時に記録を取ろうと何度も試みた。しかし、それが起きている時には、言葉が話せないし、書けないことがわかった。どうにも悔しい。 まもなく、私は、その会社を首になった。退職金は、会社で借りていた車のリース料を、半年間支払ってくれるというものだった。当面、動き回れる車だけはあるわけだが、ふくらみきった生活を、最低限まで切りつめなければならない。経営者には失業保険がない。切りつめても2~3ヶ月しかもたないなら、思い出のジャカルタでも行ってみようかなと思っていた。「トランク1つの人生さ」
(いいなあ・・・好きです。この雰囲気)
|
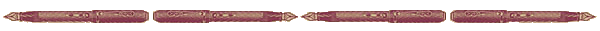 |


