


潜水艦を作ろう



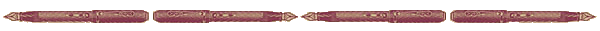 | ||
|
潜水艦を作ろうという話しを聞いたのは、雀荘でも顔を知られるようになり、私の定位置を店の人からも認めてもらえるようになった頃だ。 日本の高度成長が始まっていた。日本でも週休2日制を導入すべきだという話しを、通産省が音頭をとって呼びかけていた。勤めていた会社の社長の友人が、今度、新しい会社をはじめるという。その会社では、新しいレジャー機器を開発して売ろうという計画を持っている。レジャー用の個人向け小型潜水艦を作れば売れるだろうという話しだ。社長から、ちょっと手伝いに行ってこないかと言われた。 私は、大学では宇宙工学を専攻していた。しかし、卒業設計のテーマを考えたあげく、宇宙も海も同じ圧力差のある世界だと思い立って、潜水艦を設計することにしたのだ。流体実験も行っていたし、構造設計もできていた。確かに、専門家ではあった。 この卒業設計は、教授会で議論になって、困ったらしい。卒業設計として認めるか否か。優秀な成績であると評価すべきか、大学が考えていたテーマではないから留年させるべきか。私の担当教授が、後で話してくれた。幸い優秀なる成績の方が選択されて、卒業できた。しかし、次の年から、テーマが厳密に規定されるようになってしまった。後輩に悪いことをしたのかも知れない。 (なんで、宇宙関係の仕事につかなかって?。当時は、皆でヘルメットをかぶって、ロケットを肩にかついで発射台まで運んでいたんだよ。え~んやこらサ、え~んやこら。そんな力仕事はしたくなかっただけだよ。) その新会社は、六本木にあった。かっては誰でも知っていたアマンドという喫茶店の裏に、小さなビルがあり、そこの細い階段を屋上まで登って行く。屋上に出ると、その隅っこに、プレハブの建物がある。これが新会社であった。雨の日は、ビルの入り口で傘をとじても、屋上で再び開かなければならない。夏は、もろに暑く、冬は、ストーブをつけていても寒い。飯場にあるようなプレハブであった。 そこに入り浸っているうちに、勤めていた会社の仕事よりも面白く感じてきた(当たり前だ・・・遊んでいただけだから)。これが2番目の会社である。最初の会社で3ヶ月分程たまっていた給料の前借りを清算するので、ちょっと苦労をしたが、まもなく会社をかわった。 個人用の潜水艦について調べ始めたら、すでに自宅で潜水艦を作っている人が居ると聞いた。早速、皆で会いに出かけた。その家は、都心でも、ちょっと交通が不便な場所にあった。潜水艦を作っているオジサンの家は、アパートの2階にあり、4畳半か6畳程度の狭い部屋だったように思う。奥さんも子供も居た。そんな家族が住んでいる狭いアパートで、オジサンは、確かに潜水艦を組み立てていた。潜水艦は、部屋をいっぱに占領しており、生活の場は、ほとんど残っていなかった。あれは、72年の夏であった。 新会社の社長が、ふと疑問をもらした。「この潜水艦が出来上がったら、どうやって部屋から出すつもりですか?」。オジサンは、びっくりしたような顔をした。そこまで考えていなかったようだ。この潜水艦が、その後、どうなったか謎である。 古代ギリシャの絵にも潜水用ヘルメットの絵が残っている。空気の管を、水中の甕につないで、このカメをかぶる仕掛けである。しかし、この仕掛けでは、水中で圧力を受ける潜水夫が、ものすごい肺の力を持っていないと息ができないだろう。実際的な潜水艦は、アメリカの南北戦争で使われたものではなかったかと記憶している。樽のような中に入って、水中を進む仕掛けであるが、これは全部が水中に沈むわけではなくて、乗員の頭の部分は水上に出るように設計されている。 しかし、今はどうなっているか知らないが、潜水艦を作っても、そう簡単にテストも出来ないことを知った。許認可というのが面倒なのだ。そして、六本木でウロウロしているうちに、再び、文無しに陥っていた。収入のある仕事をしていなかったのだから当然である。 当時は、本当に大人の街であった六本木で、高級クラブのママさんから、御飯を食べさせてもらったりしていた。銀座の雇われママさんは、六本木に高級クラブを持っていた。夜中に銀座の店がはねると、六本木へやって来た。クラブでは、お客さん達が1万円札を何枚もきっていたと思うのだが、私達若者は、いつも千円札が1枚だった。かっては、道のどんずまりであったが、今は、道路が通ってしまった。そこを通るたびに、かっての綺麗なお姉さん達は、今頃どうしているのだろうかと懐かしく思い出す。 丁度、その頃だ。北アフリカの海岸沿いに、テントを使って高い人工山脈を作れば、サハラ砂漠を緑化できるという話しを聞いたのは。いつだったか、デンバー空港で、その技術が使われているのを見た時は、懐かしくも嬉しくもあった。NHKのディレクターが、ドキュメンタリーの話しを持ってきたのも、その頃だ。 とにかく生活費を稼がなければならなくなっていたので、いつのまにか潜水艦の話しは皆が忘れていった。
|
||
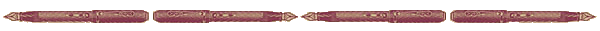 |


